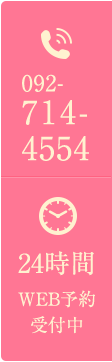一般的に、別居の事実は、破綻を推定させる一つの要素であり、必ずしも破綻の結果であるとも、破綻の原因であるとも認められません。本来、破綻の事実の認定は、夫婦間の諸事情により認定されるもので、別居自体により認定されることはあり得ません。
しかし、諸事情により破綻の事実が証明されない場合、別居の期間が破綻を証明する結果になることがあります。
本来、夫婦は両性の合意において成立するものですから(憲法の定め)、片方が嫌だと言えば、夫婦関係は成り立たないことになります。しかし、婚姻も契約の一種ですから、片方が勝手に嫌だというのを全て認めることは、安易な契約違反を認めることになります。
そこで、民法770条は、夫婦関係が破綻していることをもって、法的な離婚を認める条件となしています。ただ、かっては、民法770条の解釈を有責主義によるものと解釈され、相手の有責性を証明しなければ、離婚が認められないあるいは有責者からの離婚は認められないという解釈が採られていましたが、現在は、破綻していれば離婚を認め、例外として離婚を認めることが権利濫用に該当する場合にはこれを認めなかったり、附帯条件を厳しくすることになっています。
そこで、破綻自体の証明が困難である場合に、別居していれば、破綻している蓋然性が強いことに着目されて、別居期間何年以上であれば、破綻が認められると説明する専門家もいますが、別居は、あくまで破綻の一つの判断要素に過ぎないので、同居中でも、他の要素での破綻が証明されれば、離婚が認められますし、破綻の期間が長期に及んでも、権利濫用に該当する場合には、離婚が認められません。従って、原則として、別居期間の長短のみでは、判断基準とはなり得ません。
別居期間が、数カ月でも、片方の離婚の意思が固く、他方が関係修復の努力をすることなく相手を批判ばかりしている場合には、直ちに破綻の事実が認定されても仕方がありません。他方、長期別居でも、それが単身赴任や、定期的に交流があったり、経済的な保障関係が認められば、容易には破綻の事実は認められません。
東京高等裁判所平成27年(ネ)第1064号離婚等請求控訴事件同28年5月25日判決は、破綻原因の主張事実は証明されないし、別居期間3年5カ月は(同居期間10年)短い等として離婚請求を棄却した原審(東京家庭裁判所立川支部)を取り消して、別居期間が4年10カ月にわたった、離婚を認めていますが、同原審の判断には多いな疑問が認められます。破綻とは、夫婦関係の回復可能性が認められないということですから、片方の意思が固かったり、相手方の修復への努力が強く認められなかった等の修復実現可能性が具体的に認められない場合には、修復不可能と言うのが世間の常識だからです。
経験則的に見て、同居中に特に破綻原因が認められなかった夫婦でも、年単位を越せば、修復はあり得ないと考えられます。他方、別居後間もなく他の異性と男女関係にあることが認められた場合、破綻後の行為であるから離婚原因にならないという主張は認められないというか、その関係は、経験則的に見て、別居以前から存在したものと認めるのが、合理的と判断されると思慮します。別居後の男女関係は、破綻の原因ではないという古い先例がありますが、その事案は、養子に入ったが、理不尽に追い出され、10数年後に相手が見つかって一緒になったと言う具体的な事実認定がなされているものであり、現在においては、少なくとも年単位を経ないと、他の異性との男女関係が発覚した場合、破綻の原因ではないという主張が通るのは難しいのではないかと思慮します。
すなわち、多くの判決を見ていると、同居期間中の破綻が証明されなくても、片方の意思が固く、相手方の具体的な修復に向けての行為が認められなく、特別の事情が認められない場合には、別居が1年を超えると、破綻と認定される場合が多いと、判断されます。